| 礼拝のお話し(2016年9月)要約 |
|||
|
|
|||
| 9月25日 佐藤義則牧師 「天より与えられる永遠の住まい」召天者記念礼拝(コリント後書講解9) 聖書(新改訳) コリント人への手紙第二 5章1-5節 ☆「地上の幕屋」とは、私たちが今生きている世界のことである。身近なこととして言えば、私たちのこの地上における住居のことであると言える。目に見えるものは一時的であって、いつか朽ちて行く。最近、地震や台風による災害が相次ぐ。家屋が倒壊し大水に流される。しかし聖書は言う。地上の住まいを失っても、私たちには天より与えられる永遠の住まいがある。今の世界はいつか破局を迎える。神は新しい天と地を創造され、主の十字架によって贖われた人々は神の御国に迎え入れられる。私たちにとってこの地上での生活は寄留の生活、目的地に到達するための旅路に過ぎない。永遠の住まいを得るなら、死はいのちに呑まれている。だから死に対する恐怖はない。主を信じる者には聖霊が与えられ、天の御国を受け継ぐことと永遠のいのちが与えられていることを確信するからである。 ☆私たちはこの地上にあってうめく。だから永遠の住まいを慕い求める。しかし、重荷を負ってうめくことは決して悪いことではない。それが、主が負わせて下さる重荷、即ち十字架なら、嫌々ながら負う重荷ではない。他者のために負う重荷は潰されることなく耐え得る。愛する者のためならばなお更、力が湧く。 ☆この地上での務めを果たすなら、永遠の住まいが私たちを待っている。私たちはそこで死別した家族、愛する人たちと手と手を取り合い再会するのである。 |
|||
|
|
|||
| 9月18日 佐藤具子牧師 「苦しむ者を見過ごしにできない神」 聖書(新改訳) 士師記 10章6-16節 ☆トラ(22年間)、ヤイル(23年間)が士師である間は、イスラエルは安泰でした。しかし彼らが死んだ後、イスラエルは再び神に対して悪を行い、偶像を礼拝し、外国の迫害を受け苦境に陥ります。18年間の迫害、苦しみの後、イスラエルはようやく悔い改め、主に助けを求めました。士師記の1サイクルがここに出てきます。民の背信→外国からの迫害・苦境→神への悔い改めと叫び→神の助けです。 ☆ イスラエルの民は「私たちは、あなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバアルに仕えたのです」と告白しましたが、それに対し神は「あなたがたが選んだ神々があなたがたを助けるがよい」と、手を差し伸べません。神の願いは、神がイスラエルの民をどれほど愛しているか気づいてほしいと願ってのことでした。 ☆ 再度、民が、「私たちは罪を犯しました」と告白し、外国の神々を捨て去る姿を見て、神は、彼らの苦しみを見るに忍びなくなったのです。神に背き続ける私たちが、主のもとに帰ってくるのを神は待っておられます。苦しむのを見過ごしにできないのです。 ☆ 私たちにとって偶像とは何でしょうか? 家族や財産、才能等々も神より優先することがあります。さらに自分自身が偶像になるときがないでしょうか? 生活の中心は自分、物事の判断基準も自分にあるということが、私たちは多いものです。 ☆ 神の愛に立ち返るために、第一に過ちを認め告白すること、第二に神を生活すべての中心におくこと、そして委ねる(重い石を転がす)ことです。神は必ず省みてくださいます。 |
|||
|
|
|||
| 9月11日 佐藤義則牧師 「神の限りない愛」 伝道礼拝 聖書(新改訳) エレミヤ書 31章3節 ☆主は遠くから、私に現われた。「永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した。それゆえ、わたしはあなたに、誠実を尽くし続けた。」 ☆聖書は、「愛の書」と言われる。聖書には「愛」という言葉が幾度も出てくる。それでは「愛」とは何か? 日本に初めてキリスト教信仰が伝播されたのは戦国時代のことである。カトリックの宣教師が聖書の言葉を邦訳するにあたってもっとも苦心したのは「神の愛」である。当時「愛」という言葉はあったが、多分に誤解を受ける言葉で真意を伝えるものではないとし、「天主(デウス)のご大切」と訳された。愛は愛する対象を大切にすることであるという。名訳と言わざるを得ない。恋愛もこの神の愛に倣って、相手を大切にする愛であってほしいと願う。相手のことをどこまでも考える。相手を不幸にすることは決してしない。相手を利用せず、欲望のはけ口にしない。 ☆旧約聖書の中で、神の愛はヘセド(誠実)という言葉が使われる。神の愛は、誠実そのものである。神の愛は限りない愛であって、変わることがなく絶えることがない。その愛は、御子イエス・キリストの十字架の上にこそ表わされた。正しい者のために死ぬ者はない。情け深い人のためだったら死ぬ人があるいはいるかもしれない。しかし、主イエスは、私たちが罪深かった時、私たちのために、十字架の上で死なれたのである。ここに神の愛が明らかにされたのである(ローマ5:7-8)。 |
|||
|
|
|||
| 9月4日 佐藤義則牧師 「見えないものにこそ、目を留める」 コリント後書講解8 聖書(新改訳) コリント人への手紙第二 4章16-18節 ☆「私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです」(18節)。見えるものとは、この世の富と栄誉である。それに対して目に見えないものとは、主が天において賜わるもの、即ち天の御国と、主と同じ栄光の姿に変えられるという栄化の恵みである。目に見えないものは忘れやすくないがしろにされ、つい、目に見えるものに心魅かれてしまう。だから、パウロはエペソ1:17‐19で、聖霊によって私たちの霊の眼が開かれ、天において受け継ぐ富が如何に富んだものか、主を信じる者に働く神の力がどんなに偉大であるか知ることができるように祈っている。 ☆もうひとつの視点から、見えるものとは、私たちの置かれた状況と私たち自身である。嵐に見舞われ、その荒波を見たら、あのペテロのように波間に沈んで行くしかない。主イエス様から目を離さないでいるなら、荒波の上でも悠然と歩いて行くことができる。私たちは自分自身を見て失望する。特に、他人と比較して「自分などは駄目だ」と思ってしまう。自分は駄目だからこそ、主イエスを信じ、主イエスに依り頼む。よく言われることは、状況と自分を1度見たら、主を10度見る。見えないものにこそ目を留める。そうすれば、老後に不安をいだくことも、他人と比べて意気消沈することもないのである。 |
|||
|
|
|||
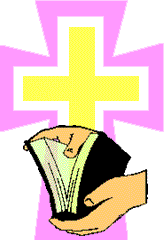 こちらから、最近のお話を録音で聞けます。 こちらから、最近のお話を録音で聞けます。 |
|||